☆☆☆☆
今井 宏平
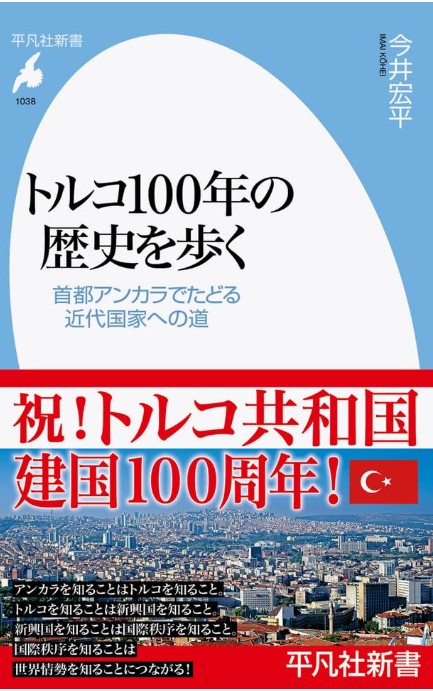
トルコ100年の歴史を歩く: 首都アンカラでたどる近代国家への道 (1038;1038) (平凡社新書 1038) 新書 – 2023/9/19
作者はトルコに留学されていた経験があるようです。トルコの近代史的な部分を首都のアンカラを中心に記述しています。
さすがに私もトルコという国は知っていました。なんとなく興味もあります。アジアの左端、ヨーロッパの右端。でも正直なところあまり詳しく知りませんでした。この本を読むことでトルコ共和国建国の父と言われるケマルパシャがなぜケマルアタチュルクと呼ばれるのかわかりました。
できの悪い高校生だった時に習ったオスマントルコ帝国がどのような国家だったのか少し理解が深まりました。オスマントルコ帝国というのは近代まで続きましたので、まあイスラム教を信じる強大な帝国という印象でした。間違ってはないと思いますが、ここに別の視点も加わりました。多民族の専制国家だということです。私はオスマントルコ帝国と書いてます。今はそう言わないようです。今はオスマン帝国。トルコ人の国家というのはトルコ共和国が初めてだから、ケマルアタチュルクは建国の父と言われているようです。
第一次世界大戦、第二次世界大戦を経て世界は民族自決の方向に進んでいきます。日本人からすると民族自決は普通のことで「そりゃそうだよね」という感じです。多民族国家というのはどちらかというと戦争であちこちを侵略して、自民族以外の民族を制服して統治している国という印象です。どっちがいいかというと民族自決の方がなんとなく正しいような気がします。近代から現代のバルカン半島の事例やアフリカの事例からは民族自決が正義かどうかは何とも言えません。
歴史を見るとオスマン帝国が小アジアから北アフリカ、イベリア半島を支配し、かたやオーストリアを中心にハプスブルク家が西ヨーロッパを支配していた時代もあります。その時代は生きるのが大変な恐ろしい時代だったのかどうかは私にはわかりませんが、想像するに今のような情報通信網や交通網などがないということはとりあえず税金とれるところが自分の領地と言う考え方だったのではないでしょうか。そう考えると要するに「お金払っておけば、親分はあんまりうるさいこと言わない」そんな時代だったんではないでしょうか。私の乏しい知識でもその頃の大帝国はそれほど帝国臣民に対して宗教的な締め付けはなかったような気がします。おそらく差別はあったと思います。この本を読むとオスマン帝国は多民族国家なので第一次世界大戦後、西ヨーロッパ諸国が小アジアを勝手に分割して自分の領土にしようとしたときに、ケマルアタチュルクがトルコ固有の領土を守ったという風に書いてあります。そこがトルコ人のケマルアタチュルクを信奉する理由のようです。ケマルアタテュルクは民族愛に燃えて、西ヨーロッパ諸国と戦い勝利を収め、現在のトルコ共和国の領土を守った英雄です。
話はそれますがトルコには人類最古の宗教遺跡と思われる遺跡があります。ギョベクリ・テペです。すごく興味があります。1万1千年前ほどの遺跡のようです。ということは農耕が始まる前です。農耕が始まる前に人が集まって宗教的な儀式などを行った可能性があります。本当に宗教というのは罪深いものですね。
トルコ100年の歴史を歩く: 首都アンカラでたどる近代国家への道 (1038;1038) (平凡社新書 1038) 新書 – 2023/9/19
説明
《目次》
第1章 西洋化とイスラームのはざまで
首都の構成と人口の変遷、圧倒的な人気を誇るムスタファ・ケマル、西洋化に基づく国家建設の理想と現実、クルド・ナショナリズムなど
第2章 郊外都市への変貌
都市化と住宅問題、トルコの中でも地震が少ない、都市化と飲食業、車の普及と充実したバス網など
第3章 つわものどもが夢の跡
政治家たちの足跡を追って、第二代大統領イスメト・イノニュと「ピンク邸宅」など
第4章 デモ・クーデター・テロの記憶
行政の中心地=政変の中心、アンカラの中心地、クズライでのデモなど
第5章 外交と政策決定の中心地
トルコの地政学的特徴、地政学的特徴に即した外交、外交機関としての外務省と移民局など
《概要》
2023年10月、トルコ共和国は建国100年を迎える。世界中の国々を見渡してみれば、まだ若い国ではある。しかし、その地理的な位置や宗教的立場から近年の国際政治・経済の場面でその存在感を高めつつある。
そのトルコの首都は「アンカラ」だ。観光地と知られ、華やかなイスタンブールとは違い、アンカラにはトルコ大国民議会や大統領府や省庁などの政治関連の建物や難関大学などが建ち並び、どちらかといえば地味でお堅いイメージだ。しかし建国の父ケマル・アタトゥルクが眠る廟やケマルの銅像は、トルコの人々の精神的な拠りどころとして大切にされている。また近年、大型ショッピングモールや流行りのカフェやレストラン、欧米資本のホテルなどが数多く建てられ、トルコの経済発展を垣間見ることもできる。一方で、クーデターやデモ、テロが起きた公園や通り、標的となった大学があり、そこには犠牲者を悼む碑などを目にする。つまり、アンカラはトルコの首都であるとともに、トルコの100年の歩みそのものなのである。
本書はアンカラ市内の政府関連施設や博物館、モスクや大学、そして主要交通機関を紹介しながらトルコ共和国100年の歴史を多数の写真とともに読み解くもの。現代のトルコ情勢を長きにわたり調査を行ってきた現地在住の気鋭の研究者ならではの視点満載の1冊。
今井宏平
日本の政治学者。専門は国際関係論、中東地域研究。とくに現代トルコの政治・外交を研究。アジア経済研究所海外派遣員(在アンカラ)。
略歴
長野県生まれ。2004年中央大学法学部政治学科卒業、2006年同大学大学院法学研究科(政治学専攻)博士前期課程修了。 2006年4月同大学院後期課程に進学し、同年秋に中東工科大学へ留学。2011年に同大学国際関係学部博士課程修了(Ph.D. )[2]。その後2013年、中央大学大学院法学研究科(政治学専攻)博士後期課程修了。
2013年、論文「トルコ公正発展党政権の中東政策:地域秩序安定化の試みとその挫折」にて中央大学より博士(政治学)の学位を取得。日本学術振興会特別研究員を経て、2016年よりジェトロ・アジア経済研究所研究員。
