☆☆☆☆
松尾 太加志
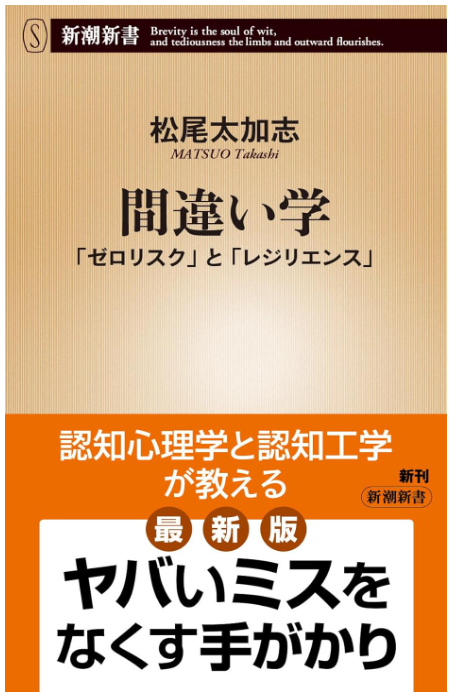
間違い学:「ゼロリスク」と「レジリエンス」 (新潮新書 1048) 新書 – 2024/6/17
間違いは誰にでもあるものです。
これは常識です。「誰にでも」とは人間が前提ということですね。
この本は間違いを起こす原因を分析し、その原因を究明し問題に対処することを目的としているようです。
分析はできるだけ客観的、科学的に実施されているようです。ただし、事例件数には限りがあり不変的な法則を見出すというものでhないような気がします。
途中から「ヒューマンエラー」に注目する形になっています。機械と人間を比較すると圧倒的に人間のまちがいが多いことは周知の事実です。「ヒューマンエラー」を減らすためのポイントを明示しています。しかし、それでも「ヒューマンエラー」はゼロにはなりません。むしろ、「ヒューマンエラー」が発生することを前提にしてシステムを「ヒューマンエラー」が起きても大ごとにならない仕組みが大事と説いています。
「そりゃそーだなー」と思いました。機械の間違いも人間に由来するものが多そうです。
「ヒューマンエラー」が起きても大ごとにならない仕組みを構築する方が功利的・合理的と思いました。
「間違い」を突き詰めて考えると、人間が勝手に「これは間違いだ」と判断したものが「間違い」となります。極めて人間依存の考え方です。自然界には「間違い」は存在しないのではないでしょうか?
要するに人間にとって不利益なことが「間違い」です。つくづく人間というのは傲慢ですな。
改めて実感しました。
間違い学:「ゼロリスク」と「レジリエンス」 (新潮新書 1048) 新書 – 2024/6/17
説明
手術患者の取り違え、投薬ミスによる死亡事故、手動遮断機の操作ミスで起きた踏切事故――あらゆる「ミス=間違い」は、人が関わることで生じている。しかし、生身の人間である以上、間違いを100%なくすことは不可能だ。なぜ、どのように間違いは起こるのか? そのミスを大惨事につなげないためにはどうしたらいいのか? 世の中にDXが浸透する現状もふまえ、最新の知見をもとに徹底分析。
はじめに
第1章 ヒューマンエラーがもたらす事故
手術で患者を取り違えた事故【事例1-1】/複数のエラーが生じて事故に至る/どうすべきだったか/リストバンドの装着ミス【事例1-2】/ITやDXは新たなヒューマンエラーを生み出す
第2章 ヒューマンエラーとは
キャッシュレス決済での失敗【事例2】/本来できたはずなのに/エラーとそうでない場合の違い/ヒューマンエラーの定義/モノや機器と関わるからエラーが生じる/AIも万能ではない
第3章 エラーをした人は悪いのか?
遮断機を上げざるをえなかった開かずの踏切の事故【事例3】/不完全なシステムを人が調整している/システムの問題がヒューマンエラーを生む/人を責めない対策/意味のない「気をつける」対策/注意すると改善されるという誤謬/後知恵バイアスによる指摘―後だしじゃんけん―
第4章 外的手がかりでヒューマンエラーに気づかせる
欠席者を合格にしてしまった入試ミス【事例4】/外的手がかりで防止策を検討/外的手がかりを考えてみることが大事
第5章 外的手がかりの枠組みでエラー防止を整理
インターホンの配線間違い【事例5】/文書で気づかされる/表示で気づかされる/対象で気づかされる/電子アシスタントで気づかされる/人(他者)から気づかされる/外的手がかりの効果と実現可能性/5つの枠組みで防止策を現場で考える
第6章 そのときの状況がエラーを招く
薬の処方ミスによる死亡事故【事例6】/さまざまな背景要因がエラーを誘発/医師のおかれた多忙な背景/モノやシステムの改善によるエラー防止策
第7章 外的手がかりは使いものになるのか
照合せずに輸血をしてしまった【事例7】/外的手がかりは使ってもらえるか?―動機づけ理論―/人の行動は誘因と動因で決まる/外的手がかりは何を防いでいるのか/行為をどうとらえるか――行為の制止、防護、修正/外的手がかりだけでヒューマンエラーは防ぐことができるのか
第8章 IT、DX、AIはヒューマンエラーを防止するのか
人は進化していない/人を介さないことでエラーがなくなる/電子アシスタントによるエラーに気づかせるしくみ/エラーに気づきやすいインタフェースが可能か/ネットワーク上の外的手がかり/人間をどう活かすか
第9章 ゼロリスクを求める危険性
新型コロナウイルスへの対処の異常さ/複雑なシステムには必ずリスクが/Safety-I, Safety-IIの考え方/感染者ゼロを目指すSafety-I、ウィズコロナのSafety-II/人間というシステムに合うのはSafety-II/レジリエンスという考え方/リスクとベネフィットを考える/人工知能がうまくいくのは/エラーに気づいてうまく対処できればよい
松尾太加志
1958(昭和33)年生まれ。九州大学大学院文学研究科心理学専攻、博士(心理学)。北九州市立大学特任教授(前学長)。著書に『コミュニケーションの心理学』(ナカニシヤ出版)など。
