☆☆☆☆
マイケル マーモット (著), Michael Marmot (原名), 鏡森 定信 (翻訳), 橋本 英樹 (翻訳)
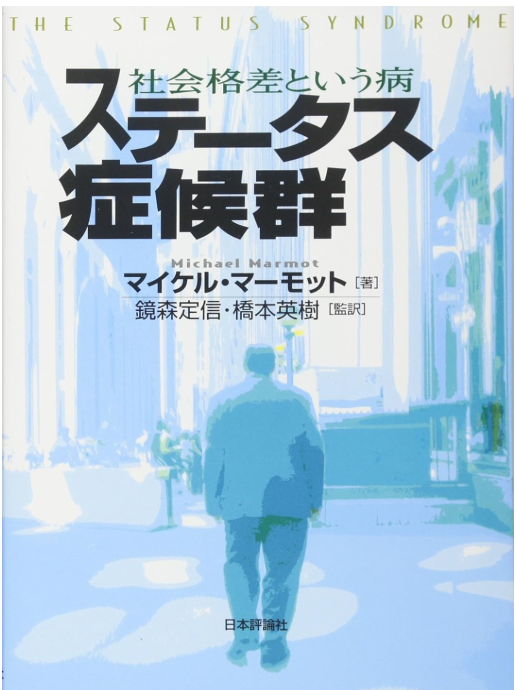
ステ-タス症候群: 社会格差という病 単行本 – 2007/10/1
健康の格差論。生活の質や経済的な格差だけでなく公衆衛生的な健康にも格差があるという本です。一般的には裕福な人々は貧乏な人々と比較して健康配慮意識が高く、充分な医療ケアを受けることができて、過酷な労働に従事していない、精神的にも穏やかに暮らして、いるという認識があります。しかも教育水準が高いために不健康な習慣を排除する傾向にあります。そりゃ健康だし、長生きするだろう、と推測できます。何をいまさらと思いました。
作者は長年公衆衛生に携わり、イギリスの「ホワイトホール」の公務員の情報を元に研究をされたようです。「ホワイトホール」は日本でいう「霞が関」で公務員が跋扈する街のようです。公務員=裕福なものもいるが、そうでないものもいる=食うに困るようなものはいない、という認識です。イギリスは階級社会といわれますので日本とは違うかもしれません。「ホワイトホール」の実績では階層が高い者の方が低い者よりも冠状血管疾患などの心臓疾患の罹患率が低く寿命が長いと指摘しています。先に述べたような総合的な理由で合理的な結果かもしれません。そうだとすると、救いはありませんが自己責任となります。「健康で長生きしたければ裕福になれ。」
ヒヒの研究も同様に比較されています。ヒヒも同様に上位のヒヒは下位のヒヒより健康で長生きなようです。ヒヒの場合は上位にいるためには下位のヒヒとの格闘などが多くなる傾向がありますので驚きです。まさか、上位のヒヒは肥満防止のエクササイズや禁煙をしているということはないでしょう。
詳細は読めばわかりますが、一番重要なポイントは「自分の人生・生活を自分でコントロールできるかどうか」のようです。そのような精神衛生上の自由感が身体的な寿命に影響するとは驚きでした。
ステ-タス症候群: 社会格差という病 単行本 – 2007/10/1
説明
格差論の名著完訳! 健康の社会格差=ステータス症候群の原因を理解し、充実した人生を送るために必要な社会づくりの指針を示す。
サー・マイケル・マーモット
ロンドン大学の疫学と公衆衛生学の教授。ロンドン大学の健康の公正研究所の責任者。カリフォルニア大学バークレー校のレナード・サイムに師事し、1975年、日系米国人における文化変容と冠動脈疾患の研究で博士号を取得。1976年にロンドン大学衛生熱帯医学大学院に移り、ドナルド・ライドとジェフリー・ローズが始めていた英国公務員男性の職階と健康に関する研究(ホワイトホール研究)に参加する。のちに英国公務員男女を対象としてさらに範囲を広げた研究(第2期ホワイトホール研究)を行った。WHOの健康の社会的決定要因委員会(2005-8)と、社会的決定要因と健康格差に関するヨーロッパ報告の責任者を務めた。勧告はWHO総会や多くの国で採用された。英国政府も社会的要因と健康の不平等に関する報告を指揮を任命した。マーモット報告とその勧告はイングランドの4分の3の自治体で現在、取り組まれている。2010年から2011年の英国医師会長を務め、2015年から2016年の第66代世界医師会長を務めた。
イギリス学士院フェロー、英国医学アカデミーフェロー、王立内科医協会フェロー。2000年にエリザベス女王からナイト(Knight)の称号を授与された。2015年プリンス・マヒドール賞受賞。
